PDCAというと、ビジネスパーソンなら誰でも知っているパフォーマンス改善のためのフレームワークです。なので
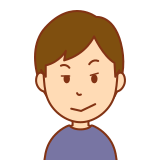
そんなのとっくに知ってるし・やってるよ
と思ったかもしれません。
でも、それをスモールビジネスならではのやり方でやると売上アップはもちろん、設定したさまざまな目標達成にびっくりするほど役に立つことはご存じですか?もし知らなければここでお伝えしますので、明日から売上アップ、業務改善にお役立て下さい。
結論から言うと、スモールビジネスならでは売上アップPDCAの回し方は
ことです。
スモールビジネスならではの「びっくりするほど成果の出るPDCA」とは
このブログをお読み下さっている方は既にご存じの通り、スモールビジネス成功の秘訣は
- 既にニーズがはっきりしている市場で
- 大企業が取り組まない(小さすぎて興味を示さない・面倒臭くてやる気がない)領域を設定し
- その領域で「〇〇と言えば・・・」であなたの会社(商品)の名前が真っ先に挙がる
ようにすることでした。
このようなスモールビジネスの特徴や成功パターンを前提として、今回は売上アップに直結するPDCAの回し方についてお伝えします。
PDCAの回し方とは言え、一番大事なのはゴールです。PでもDでもCAでもありません。
もう一度言います、大事なのはゴールです。なので、そのあたりから説明していきます。
ゴール
スモールビジネスがPDCAを使って成果を出す場合、
- 小さなゴール
- 短期間でのゴール
を設定することがなにしろ重要です。
まずスモールビジネスにおける「成果プロセス」は大企業や大きなプロジェクトと違うことを認識して下さい。スモールビジネスの成果プロセスは「早く・小さく・確実に」が原則です。なので「1年後にいくら」とかのゴール設定はダメ。
時間的には
- 長くて3ヶ月
- 最短で1ヶ月
にするべきです。
そして、数値的には
- アグレッシブ(大胆な)目標として:30%アップ
- 現実的には:5%〜20%アップ
するべきです。これを何度も何度もやる。そうすると感覚的には「気がつくとこんなに成果が出ていた」という状態になります。もちろん「気がついたらなっていた」では経営者としは失格なので、あくまでも「感覚的には」というところはご留意下さい。
そして、もちろん、これら時間的・数値的ゴール設定は、その時の状況や業界によっても変わってくることは当然ですが・・・とりあえずの目安としてご理解下さい。
P(Plan:計画)
ここは計画フェーズです。
なにを計画するかと言うと「ゴール達成のためのHow(やり方)」つまりPDCAの二つ目のフェーズであるDo(実行)策の計画です。
イメージしやすいようにシンプルな例を挙げますね。
ゴールを次のように設定します。
- 売上アップ:100
- 期間:1ヶ月
と。これはゴール設定ですよ。P(計画)ではありません。
売上アップ100を達成するためには、いくつかやり方がありますよね。
単純化すると・・・
- 単価100のものを1個売る
- 単価50のものを2個売る
- 単価20のものを5個売る
- 単価1のものを100個売る
など、やり方はいろいろです。
その中で
- 単価20のものを5個売る
ということに決めます。
そして、
5個売るためには、過去の成約率などから
- 10回のクロージング(成約のための商談)
が必要と判断。
さらに、
10回のクロージング機会を得るためには
- 30回のアポ取りが必要
と過去の経験から判断するとします。
そのために
- 3人が手分けして、それぞれ20人の見込み客に連絡する
ことにします。
これらを過去の自社のパフォーマンス実績から
- 4回転させる
と決めます。
この段階で決まったことは
- 単価20のものを5個売る
- そのためにクロージングを10回実施する
- そのために30件のアポを取る
- そのために3人の社員が、それぞれ20人の見込み客の連絡する(合計60人)
- これを4回転させる
です。
ここまでがP(計画)フェーズです。
D(Do:実行)
実行のフェーズです。
ここでは、まずは一週間実行します。ゴール設定が1ヶ月、そして4回転を目標としいているので、ここでは「一週間実行して検証する」というサイクルにします。
C(Check:検証)
検証フェーズです。
ここでは一週間で実行した進捗の検証を「計画に照らし合わせて」行います。
アポ取りを担当したのが社員Aさん、Bさん、Cさんだっとします。もちろんまだ一週間ですから、誰も成約という成果を出していません。
でも見込み客への連絡状況が以下のようだったとします。
- Aさん:5人
- Bさん:6人
- Cさん:2人
計画では「社員一人あたり20人の見込み客への連絡(合計60人)」だったので、一週間が終わったこの時点では、それぞれ5人の見込み客への連絡(合計15人)が終わっているのが理想です。でも実際はそうではなかったことがわかりました(合計13人)。このように計画と一定期間の実行結果との乖離を見つけるのが検証フェーズになります。
A(Adjust:調整)
調整フェーズです。
AをActionとしているPDCAが圧倒的に多いかもしれません。でも「早く・小さく・確実に」成果を出すことが要求されるスモールビジネスではAction よりAdjust(調整)とした方が実践的です。
一週間後の検証フェーズの直後(その日のうちに)、それぞれの社員の見込み客への連絡目標を
- Aさん:20人
- Bさん:25人
- Cさん:15人
のように「ゴール」を変更することなく担当する社員の「計画」を一部修正します。これが調整フェーズでやることです。そして、速やかに次の一週間の実行フェーズに移ります。
ここでのシンプルな例の振り返り
ここではシンプルに、社員3人の「見込み客への連絡」点における一週間後の成果が違っていたことを前提にPDCAの回し方の途中経過についてお伝えしました。
社員全員の「連絡する見込み客の人数」の進捗が計画より大きく下回っている場合には、場合によっては「単価20のものを5個売る」という当初計画(←計画フェーズで決めたこと)を「単価50のものを2個売る」と調整する(←調整フェーズでやる)など、調整・変更が必要となることもあります。
その際、単価の高い商品を売ることになった場合は、クロージングの回数も増やさなくてはいけないかもしれません。
このように全体を俯瞰しながら「計画の実行の仕方」をちょこちょこ調整することでゴール達成に導くのがスモールビジネスのやり方。
まとめ
ここではシンプルな例を挙げてスモールビジネスがやるべきPDCAの方法についてお伝えしました。
実際のビジネスでは当然複雑さが増すことになりますが、いずれにしても
スモールビジネスではゴールを小さく・短期間で設定して、常にP(計画)を柔軟に調整しながら高速でPDCAを回す
が重要であることをお伝えしました。
そもそも考え方はPDCAという古典的なフレームワークなので「本当に効果あるの?」という印象を持たれたかもしれません。でも、実はこれ「びっくりするほど成果がでる」のです。
うちの場合はどうなのよ?とご質問などございましたら、無料の「よろず相談」までお問い合わせ下さい。
無料「よろず相談」はこちらまで
ではまた
(あ)
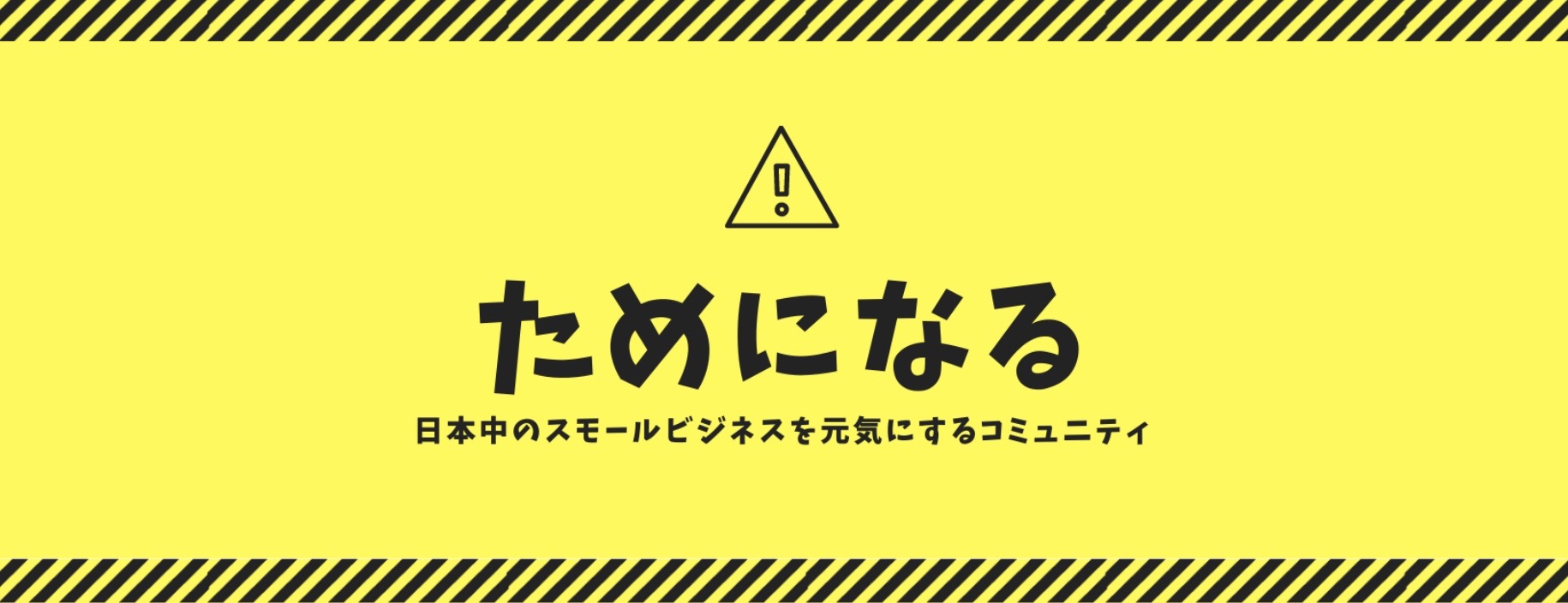
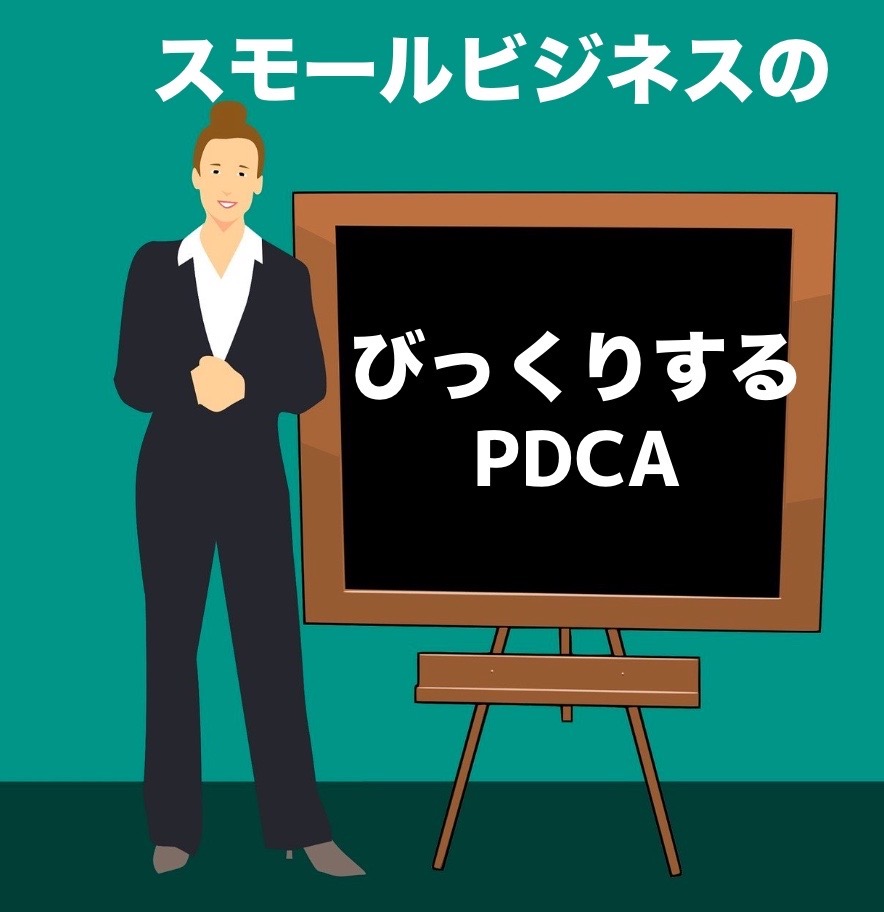
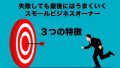

コメント